70代からの老後資金運用!安全に活かすヒント
はじめに:70代からの資産運用、「守り」と「活かし方」の新常識
「70代だけど、老後資金ってまだ運用する意味があるの?」 「年金だけじゃ足りないって聞くけど、この歳から投資は怖い…」 「もし認知症になったら、大事な資産はどうなるんだろう?」
70代からの老後資金運用は、現役世代やリタイア直後の世代とは異なる、特有の課題と目的があります。これまでの人生で築き上げてきた大切な資産を、いかに「安全に守り」、そして「賢く活かす」か。この問いは、人生100年時代を生きる私たちにとって、避けては通れないテーマです。
かつての常識では、年金生活に入ったら資産運用は「終わり」と考えられがちでした。しかし、平均寿命の伸長、そして低金利が続く現代において、現役時代に貯めた資産をただ預貯金として置いておくだけでは、物価上昇(インフレ)によって実質的な価値が目減りしてしまうリスクがあります。
この記事では、70代の皆様が安心して、そして前向きに老後資金と向き合えるよう、以下の点を中心に「安全に資産を活かすヒント」を具体的に解説していきます。特に、最近話題になっている金融庁の「プラチナNISA」の検討状況や、高齢者を狙う詐欺の手口、さらには認知判断能力の低下に備える重要性など、最新の情報や見落としがちなリスク対策についても深く掘り下げていきます。
さあ、あなたの残りの人生を、より豊かに、より安心して過ごすための「資産を活かす」新たな一歩を、一緒に踏み出しましょう。
第1章:70代からの老後資金運用──その現実と新たな目的
70代からの資産運用は、単にお金を増やすことだけが目的ではありません。人生100年時代を見据え、資産をいかに「長く持たせるか」、そして「快適に使うか」という視点が非常に重要になります。
1-1. 長寿化の現実と「資産寿命」の重要性
金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」でも指摘されているように、現代は「長寿化」が進んでいます。平均寿命が延びたことで、私たちの「老後」はかつてないほど長くなりました。
- 平均寿命と健康寿命の差: 長生きは喜ばしいことですが、平均寿命と健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)には差があります。この差の期間をいかに安心して過ごせるかが、老後のQOL(生活の質)を大きく左右します。
- 「資産寿命」の延伸: 預貯金や年金だけで生活した場合、いつか資金が底をついてしまう「資産寿命」の問題に直面する可能性があります。70代からの資産運用は、この資産寿命をできるだけ長く延ばし、人生の最後までお金の心配をしないための重要な手段となります。
1-2. 70代の資産運用の目的は「守り」と「賢く使う」
現役時代の資産運用は「増やす」ことに重きが置かれがちでしたが、70代からの運用は大きく目的が変わります。
- インフレからの「資産を守る」: 低金利が続く預貯金では、物価上昇に追いつかず、実質的にお金の価値が目減りしてしまいます。資産運用を通じて、インフレから資産を守り、購買力を維持することが重要です。
- 計画的に「資産を使う」: 老後の生活費、医療費、介護費など、将来必要となる費用を賄うために、計画的に資産を取り崩していく必要があります。運用益を生活費の一部に充てることで、元本の減りを緩やかにし、資産寿命を延ばすことが期待できます。
- 精神的なゆとりの創出: 資産が一定程度あるという安心感は、精神的なゆとりにつながります。これにより、趣味や旅行など、人生を豊かにするための活動に前向きに取り組むことができます。
1-3. あなたの年金見込み額を確認しよう
老後資金の運用を考える上で、公的年金がいくらもらえるのかを正確に把握することは、基本中の基本です。
- 「ねんきん定期便」の活用: 毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」には、これまでの年金加入期間や納付状況、そして将来受け取れる年金の見込み額が記載されています。50歳以上の方には、より具体的な見込み額が示されています。
- 「ねんきんネット」で試算: 日本年金機構の「ねんきんネット」に登録すれば、将来の働き方や年金受給開始年齢を変更して、様々なパターンで年金見込み額を試算できます。これにより、年金収入だけでは不足する金額を具体的に把握し、どの程度資産を取り崩していく必要があるのか、目標が明確になります。
- 高齢夫婦無職世帯の平均支出: 「人生100年時代の年金と資産運用戦略」資料にもあるように、高齢夫婦無職世帯の平均支出と比較して、自身の年金収入がどの程度足りないのか、あるいはゆとりがあるのかを把握する目安になります。
年金は老後の収入の柱ですが、それだけで十分な生活を送れる方は多くありません。だからこそ、今ある資産を賢く運用し、計画的に取り崩すことが、70代からの豊かな老後生活の鍵となるのです。
第2章:【重要】70代が絶対に避けるべき運用リスクと詐欺対策
70代からの資産運用において、最も警戒すべきは「リスク」と「詐欺」です。残念ながら、高齢者を狙った金融トラブルは後を絶ちません。大切な資産を守るための知識を身につけましょう。
2-1. 「プラチナNISA」検討の衝撃と「毎月分配型投信」の亡霊
最近、金融庁が高齢者向けの「プラチナNISA」の創設を検討しているというニュースが流れ、その内容が波紋を呼んでいます。特に注目すべきは、このプラチナNISAで「毎月分配型投資信託」も対象にする方向だという点です。
- なぜ毎月分配型投信はNISA対象外だったのか?: これまでのNISAの目的は、長期投資で資産をコツコツ積み上げ、将来の大きな資産を育てることにありました。毎月分配型投信は、運用で得た利益を毎月分配金として払い出してしまうため、複利効果(利益がさらに利益を生む効果)が期待できず、NISAの目的である「資産形成」にはそぐわないとされていました。
- 「グロソブ」と「タコ足配当」の記憶: 2000年代初頭に大ブームとなった「グローバル・ソブリン・オープン」、通称「グロソブ」は、高齢者に「年金代わり」として猛烈に販売されました。しかし、運用がうまくいかない場合に元本を取り崩して分配を行う「特別分配」、通称「タコ足配当」が問題となり、多くのシニア投資家が、自分の投資した資金を食いつぶしていることに気づかずに損失を被りました。金融庁もこれを厳しく糾弾してきた経緯があります。
- プラチナNISAの課題: プラチナNISAで毎月分配型投信が容認されると、高齢者が再び「タコ足配当」のリスクにさらされる可能性があります。また、対面型金融機関では、購入時の手数料が高い投資信託が勧められがちです。分配金の額だけに目を奪われず、元本が目減りしていないか、手数料は適正か、をしっかり確認する必要があります。
70代からの運用は、複利効果を重視した「長期・積立・分散」とは異なるアプローチが必要になる場合もありますが、それでも「元本を取り崩す分配金」や「高すぎる手数料」は、大切な資産を削り取る行為に他なりません。安易な甘い誘いには十分注意しましょう。
2-2. 高齢者を狙う金融詐欺の手口と回避策
詐欺師は、シニア世代の資産を狙っています。大切な資産を守るためには、詐欺の手口を知り、警戒することが重要です。
- 「必ず儲かる」「元本保証で高利回り」は詐欺の典型: 投資に「絶対」はありません。「元本保証で高利回り」を謳う話は、詐欺の可能性が極めて高いです。特に、FX取引や未公開株、社債、海外の土地、新技術への投資など、複雑で内容が理解しにくい商品を持ちかける場合は要注意です。
- 劇場型詐欺: 複数の人物が登場し、被害者を巧妙に騙す手口です。「あなたにだけ特別に…」「今しかチャンスがない」などと、急かしたり、優越感を刺激したりして、冷静な判断を奪おうとします。
- 還付金詐欺: 税金や医療費などが戻ってくると偽り、ATMを操作させたり、個人情報を聞き出そうとする手口です。役所や金融機関がATMで還付金の手続きをさせることは絶対にありません。
- オレオレ詐欺(特殊詐欺): 息子や孫を装って電話をかけ、「お金が必要」などと騙し取る古典的な手口ですが、いまだに被害が後を絶ちません。
詐欺から身を守るための鉄則:
- 知らない電話番号やメール、郵便は無視する: 身に覚えのない連絡には絶対に応じない。
- 安易に個人情報を教えない: 氏名、住所、電話番号、銀行口座番号、暗証番号、クレジットカード情報などを安易に教えない。
- 「おかしい」と感じたら、必ず誰かに相談する: 家族、信頼できる友人、金融機関、消費生活センター(消費者ホットライン188)、警察(#9110)など、必ず第三者に相談しましょう。一人で抱え込まないことが何より重要です。
- 金融庁のウェブサイトなどで最新の詐欺情報を確認する: 公的機関が発信する注意喚起を常にチェックしましょう。
2-3. 認知判断能力の低下に備える──資産凍結リスクとその対策
金融審議会市場ワーキング・グループ報告書では、「認知・判断能力の低下は誰にでも起こりうる」と警鐘を鳴らしています。もし認知症などで判断能力が低下した場合、預貯金が引き出せなくなったり、不動産を処分できなくなったりと、「資産凍結」のリスクに直面する可能性があります。
- 家族による引き出しが困難に: 原則として、本人の意思確認ができない場合、たとえ家族であっても本人の預貯金を引き出すことはできません。これは、金融機関が預金者保護のために行っている措置ですが、生活費の支払いや医療費の工面が滞る原因となります。
- 不動産取引の制限: 自宅の売却や賃貸契約など、不動産に関する取引も本人の意思能力がなければ原則行えなくなります。
- 備えとしての制度活用:
- 任意後見制度: 自分が元気なうちに、将来認知判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や医療・介護の手続きを任せる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。公正証書で契約を結び、家庭裁判所で選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人に代わって財産管理などを行います。
- 家族信託: 自分の財産を家族に託し、目的(例えば、自分の生活費や介護費に充てるなど)を定めて管理・運用してもらう仕組みです。柔軟な財産管理が可能で、本人の意思を最大限に反映させることができます。
- 成年後見制度(法定後見): 既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。本人の利益を保護することを目的としますが、財産管理の柔軟性が低い、一度開始すると原則終了しないなどの留意点もあります。
- 周囲とのコミュニケーションの重要性: 心身の衰えに応じて、本人だけでなく家族や後見人など周囲の者とのコミュニケーションも必要になります。必要に応じて早い時期から周囲の者とも関係を構築しておくことが望ましいとされています。
70代からの老後資金運用は、元気なうちに「もしも」の時に備えることが非常に重要です。早めに家族と話し合い、専門家(弁護士、司法書士、FPなど)に相談して、自分に合った対策を講じましょう。
第3章:70代からの「安全に活かす」資産運用戦略
70代からの資産運用は、リスクを最小限に抑えつつ、計画的に資産を活用していくことが重要です。積極的な「増やし」よりも、安定的な「守り」と「取り崩し」に重点を置きましょう。
3-1. リスクを避け、守りを固める運用ポートフォリオ
- 「守り」の資産が中心: 高齢期においては、株式など価格変動の大きい資産への比重を減らし、預貯金や個人向け国債といったリスクの低い「守り」の資産を中心にポートフォリオを構築することが基本です。
- インフレヘッジも考慮: とはいえ、預貯金だけではインフレリスクに対応できません。一部は、インフレに強いと言われる資産(例えば、インフレ連動国債など)や、低リスクで分散投資が可能な投資信託などを検討しましょう。
3-2. 新NISAの賢い活用──70代からのメリットとは
「新NISAは若い人向け」と思われがちですが、70代からでも非課税メリットを享受できる、非常に有効な制度です。
- 非課税メリットの享受: NISA最大のメリットは、運用益が非課税になる点です。70代からでも運用期間が10年以上あれば、複利効果と非課税の恩恵を十分に受けることができます。
- 「つみたて投資枠」で低リスク運用:
- 年間120万円の「つみたて投資枠」は、金融庁が定めた条件を満たす投資信託のみが対象です。これらは低コストで分散投資されており、比較的リスクを抑えながら運用できます。
- 毎月少額からでも、自動積立設定をしておくことで、計画的に投資を継続できます。例えば、年間で数十万円の投資でも、長期間で考えれば非課税メリットは大きいです。
- おすすめは「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などのインデックスファンドです。これらは世界経済の成長を取り込むことを目指すため、特定のリスクに偏らず、安定的なリターンが期待できます。
- 「成長投資枠」の活用は慎重に:
- 年間240万円の「成長投資枠」では個別株やより幅広い投資信託に投資できますが、70代からはリスクの高い商品への投資は極力避け、慎重に利用することが重要です。
- 既に保有している個別株や、自身がよく理解している企業の株で、配当を重視した長期保有であれば検討の余地はあります。
- 非課税保有限度額の再利用: 新NISAは、投資商品を売却して非課税枠が空けば、翌年以降にその枠を再利用できます。これは、計画的に資産を取り崩しながら運用を継続する70代にとって、非常に柔軟性の高いメリットとなります。
3-3. 安定的な運用を支える商品選び
- 個人向け国債: 元本割れのリスクが極めて低く、半年ごとに利子が支払われる安全性の高い金融商品です。金利は変動しますが、最低金利保証があり、中途換金も可能です。老後資金の「守り」の部分に最適です。
- 低リスクの投資信託: 「つみたてNISA」対象の投資信託の中から、自身の資産状況やリスク許容度に合わせて選びましょう。全世界株式型や、バランス型など、分散効果が高いものがおすすめです。
- 高配当株投資(慎重に): 個別株はリスクが高いですが、安定的に高配当を出し続けている企業の株式に、余裕資金の一部を長期投資することで、定期的な収入源とすることも可能です。ただし、企業の業績悪化や減配のリスクも理解しておく必要があります。
- 金融機関の窓口で相談する際の注意点: 対面型金融機関では、購入手数料や信託報酬が高い商品が勧められるケースもあります。必ず、提案された商品の手数料(購入時、信託報酬など)と、その商品がご自身の運用目的に合致しているかを、冷静に判断しましょう。
3-4. 計画的な「資産の取り崩し方」
資産を安全に「活かす」ためには、計画的な取り崩しが不可欠です。
- 毎月の生活費に合わせた定額取り崩し: 毎月一定額を資産から引き出し、生活費に充てる方法です。年金支給日と合わせて引き出し日を設定することで、家計管理がしやすくなります。
- 「使い切り設計」の考え方: 金融庁の意識調査でもあったように、高齢者の中には自動的に金融資産を取り崩し、年金のように定額で使える「使い切り設計」を期待する声があります。一部の証券会社では、資産を計画的に取り崩すサービスを提供しています。ご自身の資産寿命をシシミュレーションし、無理のない取り崩し計画を立てましょう。
- インフレ率を考慮した調整: 長期の取り崩しでは、インフレによって将来の生活費が増える可能性も考慮し、数年おきに取り崩し額を見直す柔軟性も持ちましょう。
第4章:お金を「活かす」ためのライフプランニングと終活
資産運用は、豊かな老後を送るための手段です。その目的を達成するためには、具体的で現実的なライフプランと、もしもの時に備える終活が欠かせません。
4-1. 70代からの人生設計──「生きがい」を具体的に描く
「家計管理とライフプラン.pdf」でも触れられているように、将来どんな人生を送りたいか構想を描く「ライフデザイン」は、年齢を重ねても重要なことです。
- 時間の使い方をデザインする: 定年後の豊富な時間をどう使いたいですか?趣味、旅行、ボランティア、学習など、具体的な活動をリストアップしてみましょう。
- 「役割」を持つことの重要性: 地域活動への参加、孫との交流、軽い仕事など、社会との接点や「役割」を持つことは、精神的な充実感につながります。
- 新たな学びと挑戦: 新しいことに挑戦する意欲は、認知機能の維持にも繋がります。学びたいこと、挑戦したいことを探してみましょう。
- 居住地の選択: ライフステージに合わせて、住居を見直すことも重要です。バリアフリー、利便性、生活コストなどを考慮し、ダウンサイジングや、サービス付き高齢者向け住宅への住み替えなども検討に値します。
4-2. 医療費・介護費への備えを具体的に
高齢期の生活において、医療費や介護費は避けられない大きな支出です。これらへの備えは、老後資金運用の計画に必須です。
- 公的医療保険・介護保険の理解: 日本の医療・介護制度は手厚いですが、自己負担分も発生します。制度の内容を理解し、自己負担がどの程度になるか把握しておきましょう。
- 高額療養費制度の活用: 医療費が高額になった場合に自己負担を軽減する「高額療養費制度」は、必ず利用できるようにしましょう。
- 民間の医療保険・介護保険の検討: 公的制度だけでは不安な場合、民間の医療保険や介護保険の加入も選択肢です。ただし、既に加入している保険がある場合は、保障内容の重複や、現在の健康状態での加入可否を慎重に検討しましょう。
- 介護の相談窓口: 介護が必要になった際の相談窓口(地域包括支援センターなど)を事前に把握しておくことも大切です。
4-3. 終活の重要性──「もしも」を「安心」に変える
終活は、残りの人生を自分らしく生き、そして大切な人に負担をかけないための重要な準備です。
- エンディングノートの活用: 自分の希望や伝えたいことを記しておくエンディングノートは、もしもの時に家族が困らないための羅針盤になります。葬儀やお墓の希望、医療・介護に関する意思、財産の一覧、連絡先などをまとめておきましょう。
- 遺言書の作成: 財産の分け方を法的に有効な形で残したい場合は、遺言書を作成しましょう。特に、家族関係が複雑な場合や、特定の団体に寄付したい場合などは、遺言書が不可欠です。専門家(弁護士、司法書士)に相談し、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。
- 相続対策: 家族への負担を減らし、円滑な相続を行うために、早めに相続対策を検討しましょう。生前贈与、不動産の整理、生命保険の活用など、様々な方法があります。相続税についても、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
- デジタル遺品の整理: スマートフォンやパソコンのパスワード、SNSアカウント、オンラインサービスのIDなど、デジタル資産の情報を整理しておくことも、現代では重要な終活の一つです。
第5章:専門家との賢い付き合い方とセカンドオピニオンの勧め
70代からの老後資金運用は、複雑な要素が絡み合います。不安を感じたら、一人で悩まず専門家の力を借りることも重要です。しかし、その選び方には注意が必要です。
5-1. 金融機関との適切な距離と手数料への意識
前述のプラチナNISAに関する記事にもあるように、対面型の金融機関では、店舗運営コストなどから、ネット証券に比べて手数料の高い金融商品を勧められる傾向があります。
- 手数料の種類と確認: 投資信託を購入する際には、「購入時手数料(販売手数料)」と「信託報酬(運用管理費用)」の2種類の手数料に特に注意しましょう。ネット証券では「購入時手数料無料(ノーロード)」が一般的ですが、対面型では3%以上かかる商品も珍しくありません。
- 複数の情報を比較検討する: 提案された金融商品やサービスについて、安易に決定せず、必ず他の金融機関やネット証券の類似商品と比較検討しましょう。
- 自分の目的に合致しているか: 営業担当者の話を聞く際は、「これは自分の運用目的に合致しているか?」「本当に自分に必要な商品か?」という視点を常に持ちましょう。
5-2. ファイナンシャル・プランナー(FP)など専門家への相談
- FPの役割: ファイナンシャル・プランナー(FP)は、家計、教育、住宅、老後、保険、税金、相続など、お金に関する幅広い知識を持ち、個人のライフプランに応じた資金計画の立案やアドバイスを行います。
- FPの選び方: FPには「独立系FP」と「企業系FP」がいます。
- 独立系FP: 特定の金融機関に属さず、相談料を報酬として受け取るため、中立的な立場でのアドバイスが期待できます。
- 企業系FP: 金融機関や保険会社などに所属し、自社の商品を提案する場合があります。
- 「CFP®」や「FP技能士1級」といった上位資格を持つFPは、より専門性が高いとされています。
- セカンドオピニオンの活用: 一つの専門家の意見だけでなく、複数の専門家から意見を聞く「セカンドオピニオン」を活用することも重要です。特に高額な金融商品の購入や、相続などの重要な決定の際には、多角的な視点から検討することで、より良い選択ができます。
- 相談する内容の明確化: 相談に行く前に、何について相談したいのか(例:老後資金の取り崩し方、相続対策、現在の資産の見直しなど)を明確にしておきましょう。
終章:まとめ──70代からの老後資金運用は「安心」と「充実」のために
「70代からの老後資金運用」は、決して難しいことではありません。大切なのは、年齢を重ねた自分自身の状況を理解し、それに合った「安全な」戦略を立て、そして「賢く活かす」ことです。
- 目的を明確にする: 資産を「増やす」よりも「守り」、そして「計画的に使う」ことを目的としましょう。
- リスクを理解し、詐欺から身を守る: 特に「毎月分配型投資信託」の過去の教訓や、高齢者を狙う金融詐欺の手口を学び、甘い誘いには絶対に乗らない警戒心を持ちましょう。
- 認知判断能力の低下に備える: 任意後見制度や家族信託など、資産凍結のリスクに備える準備を元気なうちに行いましょう。
- 新NISAを賢く活用する: 70代からでも非課税メリットは大きいです。つみたて投資枠を中心に、リスクの低い投資信託などで安全に運用益を享受しましょう。
- 計画的な取り崩しとライフプラン: 残りの人生で必要となる資金をシミュレーションし、計画的に資産を取り崩しながら、自分の理想とする「生きがい」に満ちた老後を具体的に描きましょう。
- 専門家との上手な付き合い方: 必要に応じて専門家の意見を聞き、ただし手数料や提案内容をしっかり吟味し、複数の視点から判断する習慣をつけましょう。
人生100年時代、70代はまだまだ人生の「現役」です。この大切な時期を、お金の不安なく、心身ともに豊かに過ごすために、今から「安全に資産を活かす」新たな一歩を踏み出してみませんか。
あなたの未来は、あなたの手で、より豊かにデザインできます。
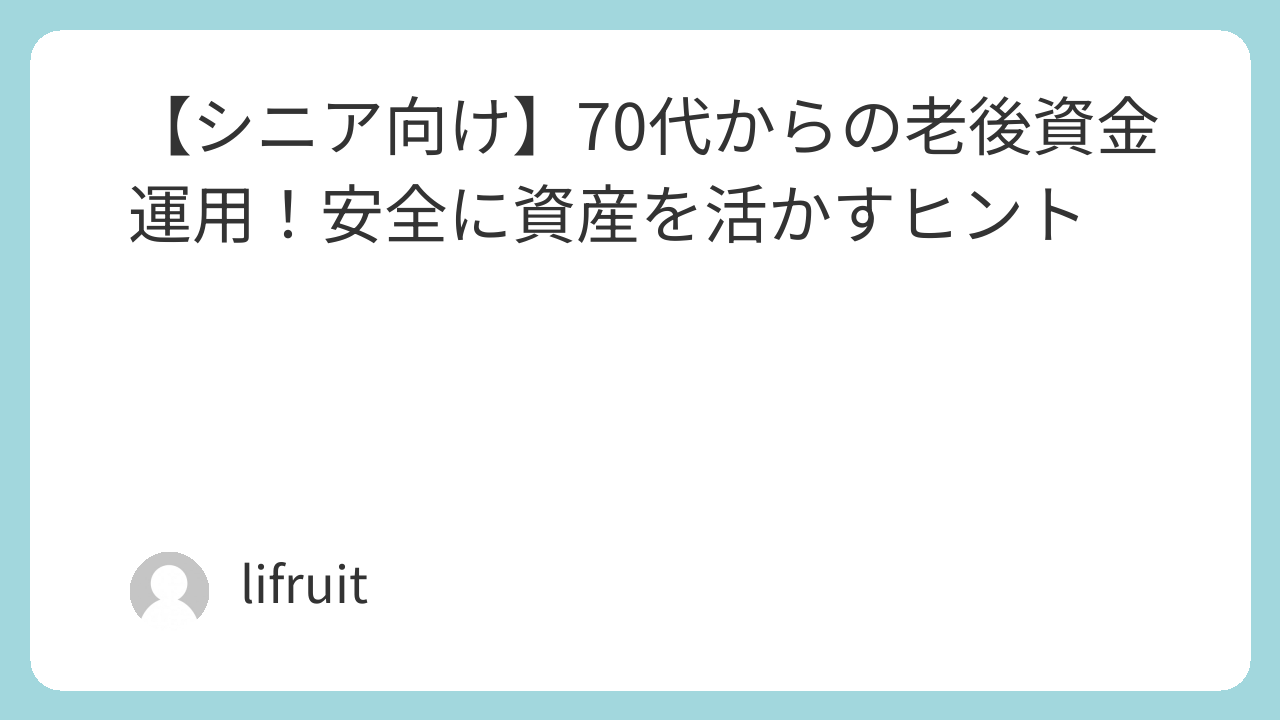
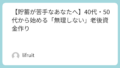
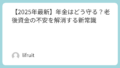
コメント