- 貯蓄苦手でもOK!40・50代の無理しない老後資金
貯蓄苦手でもOK!40・50代の無理しない老後資金
はじめに:40代・50代、貯蓄は「苦手」でも諦めないで!
「老後資金、貯めなきゃいけないのは分かってる。でも、どうしても貯蓄が苦手で…」
そう感じている40代、50代のあなたは、決して一人ではありません。日々の生活費、住宅ローン、お子さんの教育費など、現役世代は何かとお金がかかるもの。さらに、貯蓄に苦手意識があると、「今から始めても手遅れなのでは?」という不安が募るばかりかもしれません。
でも、安心してください。貯蓄は「才能」や「根性」で決まるものではありません。大切なのは、あなたの性格やライフスタイルに合った「無理しない」仕組みを作ること。そして、老後資金作りは、決して苦しい我慢の連続ではないということです。
この記事では、「貯蓄が苦手」を克服し、40代・50代からでも着実に、そして何より「無理なく」老後資金を準備するための具体的なステップをご紹介します。過去にインプットした情報に基づき、新NISAの活用法や、お金の「見える化」の重要性、さらには親世代の家計から学ぶヒントまで、多角的な視点でお伝えしていきます。
さあ、今日から「無理しない」老後資金作り、一緒に始めてみませんか?
第1章:「貯蓄苦手」をあきらめる前に:あなたの貯蓄タイプを診断しよう
貯蓄が苦手な人には、いくつかの共通する傾向があります。まずは、あなたがどのタイプに当てはまるのかを知ることから始めましょう。自分の傾向を理解することで、より効果的な「無理しない」対策が見えてきます。
1-1. なぜ「貯蓄が苦手」だと感じるのか?
貯蓄が苦手だと感じる背景には、様々な要因があります。
- 「いつの間にか」お金がなくなるタイプ
- 給料日には「今月こそ貯めるぞ!」と意気込むものの、月末には残高が減っている。何に使ったか明確には覚えていない…というタイプです。衝動買いが多い、少額の出費を気にしない、といった特徴があります。
- 「誘惑に弱い」タイプ
- セールや限定品、友人からの誘いなど、目の前の楽しみに抗えないタイプです。「今楽しむこと」を優先しがちで、未来のための貯蓄に意識が向きにくいことがあります。
- 「家計簿が続かない」タイプ
- 何度か家計簿に挑戦したけれど、結局三日坊主で終わってしまう。細かく記録するのが面倒、数字を見るのが嫌、といったタイプです。お金の流れが「見えない化」しているため、どこに無駄があるのか把握しにくい状況です。
- 「将来が漠然としすぎている」タイプ
- 老後が遠い未来すぎて、具体的にイメージできない。だから、「なぜ今から貯めなければならないのか」というモチベーションが湧きにくいタイプです。目標が不明確だと、行動も伴いにくくなります。
- 「そもそも収入が少ない」と諦めているタイプ
- 「どうせ収入が少ないから、貯蓄なんて無理」と最初から諦めてしまっているタイプです。しかし、年収300万円台からでも「勝ち組老後」を目指せるように、収入の多寡だけで貯蓄の成否は決まりません。
1-2. 大切なのは「完璧」を目指さないこと
「貯蓄が苦手」な人ほど、完璧な家計管理や、急激な節約をしようとしがちです。しかし、これが続かない最大の原因。三日坊主で終わると、自己嫌悪に陥り、ますます貯蓄への苦手意識を深めてしまいます。
「無理しない」老後資金作りで最も大切なのは、「完璧」を目指すのではなく、「継続」できる仕組みを作ること。少しずつでも、確実に、楽しく続けていける方法を見つけることが成功への鍵です。
第2章:「見える化」で無理なく貯蓄:家計管理のストレスをなくすヒント
貯蓄が苦手な人が最初にぶつかる壁が「家計管理」です。家計簿をつけるのが面倒、収支が合わない…そんなストレスをなくし、お金の流れを「見える化」することで、貯蓄はぐっと楽になります。
2-1. 家計の現状を把握する:まずはお金に「気づく」ことから
家計管理とライフプランニングにおいて、まず家庭の収入と支出を管理することが重要です。このプロセスを「家計管理」と呼びます 。
あなたが毎月、いくら収入があり、いくら何に使っているのか、漠然とでも把握していますか?貯蓄が苦手な人の多くは、この「お金の流れが見えていない」状態にあります。
「家計管理」の第一歩は、お金に「気づく」こと。完璧な家計簿は不要です。まずは、大まかな収支を把握することから始めましょう。
- 給与明細をチェックする
- 毎月の給与明細から、手取り収入を正確に把握することが貯蓄や支出の基準となります 。額面収入から税金や社会保険料が控除された「手取り収入」が、実際に使えるお金です。
- PDF資料でも、給与明細の例が示されており、支給額から税金と社会保険料を差し引くことで手取り収入が計算できることが説明されています 。
- 1ヶ月の支出をざっくり把握する
- レシートを全部取っておく必要はありません。まずは、主な支出項目(住居費、食費、通信費、交通費、被服費、教養娯楽費など)ごとに、ざっくりとでもいいので1ヶ月にいくら使っているかを把握してみましょう 。
- 家計管理シミュレーターの例では、住居費、通信費、食費などがカテゴリ分けされ、それぞれの目安が提示されています 。
- 「固定費」と「変動費」に分けるのがおすすめです。
- 固定費: 毎月決まって出ていくお金(家賃、住宅ローン、保険料、スマホ代、サブスク代など)
- 変動費: 月によって変動するお金(食費、交通費、交際費、娯楽費など)
2-2. ズボラさんでも続く「無理しない」家計管理術
「家計簿は続かない…」そんなあなたには、以下の方法がおすすめです。
- ステップ1: クレジットカード・デビットカード・スマホ決済をメインにする
- 現金払いを減らし、できるだけキャッシュレス決済に統一しましょう。そうすることで、利用履歴がアプリやウェブ上で自動的に記録されます。手書きの家計簿は不要です。
- ステップ2: 家計簿アプリと連携する
- クレジットカードや銀行口座、証券口座などを連携できる家計簿アプリを活用しましょう。連携設定をしてしまえば、あとは自動で収支が記録され、グラフなどで「見える化」してくれます。
- おすすめは、使っている銀行やカードとの連携がスムーズで、シンプルに使えるアプリです。複雑な機能は最初から使わなくても大丈夫。まずは「自動記録」の恩恵にあずかりましょう。
- ステップ3: 週に1回、5分だけ「振り返りタイム」を作る
- 週末など、決まった曜日に5分だけでいいので、家計簿アプリを開いてお金の流れをチェックしましょう。今週は何にいくら使ったのか、予算オーバーしていないかなど、大まかでOKです。
- この「振り返り」が、お金に対する意識を変える第一歩になります。「気づき」が次の行動につながります。
2-3. 「先取り貯蓄」で半自動的に貯まる仕組みを作る
貯蓄が苦手な人に最も効果的なのが「先取り貯蓄」です。これは、給料が入ったらまず貯蓄分を別の口座に移してしまう方法です。残ったお金で生活するので、無駄遣いを防ぐことができます。
- 財形貯蓄や社内預金を利用する
- 会社に財形貯蓄制度や社内預金制度があれば、給料から天引きで貯蓄されるため、一番「無理しない」方法です。給料が入る前に貯蓄が完了するので、意識することなくお金が貯まっていきます。
- 自動積立定期預金を利用する
- 金融機関の自動積立定期預金を利用し、給料日直後に決まった額を自動で積立預金口座に振り替える設定をしましょう。これも、一度設定すればあとは自動なので、手間がかかりません。
- 給与振り込み口座を分ける
- 給料の振込先を、生活費用の口座と貯蓄用の口座の2つに分け、貯蓄分は最初から貯蓄用口座に振り込まれるように設定するのも有効です。
「先取り貯蓄」は、家計管理シミュレーターが示す「毎月の収支をプラスに」する基本的な考え方でもあります。意識せずとも、自動的に貯蓄が増えていく仕組みは、貯蓄が苦手な人にとって強力な味方となるでしょう 。
第3章:「使うお金」と「育てるお金」を分ける:新NISAの賢い活用術
貯蓄の準備が整ったら、次はお金を「育てる」ステップです。特に40代・50代は、時間を味方につけつつ、効率的な資産形成が求められます。ここで活用したいのが「新NISA」です。
3-1. なぜ「貯める」だけでなく「育てる」必要があるのか?
老後資金を準備する上で、「貯蓄」だけでは限界があります。その理由は、以下の2点です。
- 低金利時代: 銀行預金だけではほとんど増えません。
- インフレのリスク: 物価が上昇すると、お金の価値は相対的に目減りします。例えば、現在の1000万円が20年後も同じ購買力を持つとは限りません。
そこで必要となるのが、「投資」です。投資はリスクも伴いますが、時間をかけて複利の効果を享受できれば、資産を効率的に増やすことが期待できます。複利の効果を体験することは、資産形成の重要な要素の一つです 。
3-2. 新NISAは「貯蓄が苦手」な人のための制度
新NISAは、非課税で投資ができる国の制度です。特に以下の点で、「貯蓄が苦手」な人に優しい制度と言えます。
- 非課税枠の拡大: 年間最大360万円、生涯で1800万円までの投資が非課税で行えます。得られた利益に税金がかからないため、効率的に資産を増やせます。
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」:
- つみたて投資枠(年間120万円): 金融庁が選定した、長期・積立・分散投資に適した投資信託に限定されているため、初心者でも安心して始めやすいです。毎月一定額を自動的に積み立てるため、「先取り貯蓄」と同じように、無理なく投資を継続できます。
- 成長投資枠(年間240万円): 個別株や投資信託など、より幅広い商品に投資できます。こちらは、ある程度投資に慣れてきたら検討しても良いでしょう。
- 非課税保有限度額の再利用: 投資商品を売却して非課税枠が空けば、翌年以降にその枠を再利用できます。これにより、柔軟な資産運用が可能です。
3-3. 失敗しない新NISAの始め方:3つのステップ
「投資って難しそう…」と感じるかもしれませんが、新NISAは非常にシンプルに始めることができます。
- ステップ1: 金融機関を選ぶ
- ネット証券がおすすめです。手数料が安く、NISA口座開設の手続きもオンラインで完結できます。
- ポイント還元があるか、アプリの使いやすさなども考慮すると良いでしょう。
- ステップ2: つみたて投資枠で投資信託を選ぶ
- まずは「つみたて投資枠」から始めましょう。投資信託の中でも、以下の点に注目して選びます。
- 全世界株式インデックスファンド: これ一つで世界中の企業に分散投資できるため、初心者におすすめです。
- 信託報酬が低いもの: 運用にかかるコストが低いものを選びましょう。
- 純資産総額が大きいもの: 多くの人が投資している安定感のあるファンドを選びましょう。
- 毎月少額(例えば月1万円からでもOK)から、自動積立設定をすることが「無理しない」ポイントです。
- まずは「つみたて投資枠」から始めましょう。投資信託の中でも、以下の点に注目して選びます。
- ステップ3: ドルコスト平均法でリスクを軽減
- 「つみたて投資」は、毎月一定額を買い付けることで、価格が高い時には少なく、価格が低い時には多く購入する「ドルコスト平均法」の効果が得られます。これにより、高値掴みのリスクを抑え、長期的に安定したリターンを目指しやすくなります。
「資産形成シミュレーター」の活用も推奨されており、複利の効果を体験することは長期的な資産形成において非常に有効です 。新NISAの積立投資はまさにこの複利の効果を最大限に活用できる方法と言えます。
第4章:ライフプランを見直す:老後を「見える化」でモチベーションアップ
貯蓄が苦手な人は、「老後」という漠然とした未来のために頑張ることが難しいと感じるかもしれません。しかし、ライフプランを具体的に描くことで、老後資金作りのモチベーションを飛躍的に高めることができます。
4-1. 「ライフデザイン」と「ライフプランニング」で未来を明確に
将来どんな人生を送りたいかについての構想を描くことを「ライフデザイン」といいます 。そして、人生の希望や計画を具体的に時系列で描くことが「ライフプランニング」です 。
「ライフプランニング」は、漠然とした老後の不安を具体的な「お金」の計画に落とし込む作業です。
- 将来の夢や希望を書き出す:
- 何歳まで働くか 、どんな仕事をしたいか 、独身か結婚するか 、子どもはいるか 、どこに住むか 、どんな暮らしをしたいか 、実現したいこと、欲しいものは何か 、といった質問に答える形で、あなたの未来の理想を書き出してみましょう。
- 海外移住、趣味に没頭、悠々自適な旅行生活、地域活動への参加…どんな小さなことでも構いません。
- イベントと必要資金をリストアップする:
- 結婚、出産、住宅購入、お子さんの教育費、親の介護など、人生には大きな支出が伴うイベントがあります 。これらのイベントがいつ頃発生し、いくら必要になるのかを具体的にリストアップしてみましょう。
- 特に「教育」「住宅」「老後」は人生の3大費用と言われています。これらに対して計画的に準備することが重要です 。
- 生涯の収入と支出のバランスを考える:
- PDF資料では、生涯の収入(労働収入、退職金、年金、資産形成による増加分など)と支出(生活費、教育費、住宅費、老後費用など)のバランスを考えることの重要性が示されています 。
- ライフプランシミュレーターを活用して、自分の人生設計に合わせたシミュレーションを行うことも有効です。これにより、年齢ごとの収入・支出や貯蓄の推移を「見える化」できます 。
- シミュレーションを通じて、「60歳になる時にマイナスにならないように」といった具体的な目標が見えてきます 。
4-2. 「見える化」された未来がモチベーションになる
具体的なライフプランを描くことで、老後資金は「漠然とした不安」から「達成すべき目標」へと変わります。
- 目標が明確になる: 「〇歳までに〇〇万円貯める」という具体的な目標ができると、日々の貯蓄や節約、投資に対する意識が高まります。
- 達成感が得られる: 月々の貯蓄額や投資の状況が「見える化」されることで、着実に目標に近づいていることを実感でき、継続するモチベーションになります。
- 「使えるお金」と「貯めるお金」の区別がつく: ライフプランによって必要な資金が明確になることで、無駄遣いを減らし、本当に使いたいものには躊躇なくお金を使えるようになります。
第5章:貯蓄体質になるための「無理しない」習慣作り
貯蓄は、特別なことではなく、日々の習慣の積み重ねです。ここでは、「貯蓄が苦手」な人でも無理なく続けられる、行動経済学に基づいた習慣化のヒントをご紹介します。
5-1. 小さな「成功体験」を積み重ねる
いきなり大きな目標を立てるのではなく、まずは達成しやすい小さな目標から始めましょう。
- 100円貯金から始める: 毎日小銭を貯金箱に入れる、500円玉貯金をするなど、まずは「貯める」という行為自体に慣れることから始めましょう。
- 「週予算」を意識する: 毎月一括で予算を立てるのが難しい場合は、1週間ごとに使えるお金を決める「週予算」を試してみましょう。1週間という短いスパンであれば、管理しやすく、達成感も得やすいです。
- 「ご褒美」を設定する: 小さな目標を達成したら、自分にご褒美をあげましょう。それがモチベーションを維持する原動力になります。ただし、ご褒美のために貯蓄を切り崩すのはNGです。
5-2. 行動経済学で「貯蓄苦手」を克服
人間の行動や心理を分析する「行動経済学」は、貯蓄の苦手意識を克服するヒントをくれます。
- デフォルト設定を活用する:
- 人は、デフォルト(初期設定)を変えることを面倒に感じる傾向があります。これを逆手にとって、「先取り貯蓄」や「自動積立投資」をデフォルト設定にしてしまいましょう。一度設定すれば、あとは何もしなくても自動でお金が貯まっていきます。
- ナッジ理論で「そっと後押し」:
- 強制するのではなく、行動を「そっと後押し」する「ナッジ」を活用しましょう。例えば、貯蓄用口座の残高が増えていくのを「見える化」するアプリやグラフを使うことで、自然と貯蓄への意識が高まります。
- 「今」と「未来」の自分を繋ぐ:
- 人は「今」の欲求を優先しがちです。老後の自分を具体的にイメージし、その未来の自分と「今」の自分を繋ぐ工夫をしましょう。老後の夢を写真やイラストにして貼っておく、老後の目標を紙に書いて常に目につく場所に置くなどが有効です。
5-3. 無駄をなくす「断捨離」と「固定費見直し」
貯蓄体質になるためには、日々の無駄をなくすことも重要です。特に効果的なのが「固定費の見直し」です。
- サブスクリプションサービスの整理:
- 利用していない動画配信サービスや音楽サービス、アプリの課金などはありませんか?一度契約すると惰性で続けてしまいがちなので、定期的に見直して不要なものは解約しましょう。
- 通信費の見直し:
- 大手キャリアを使っている場合は、格安SIMへの乗り換えを検討しましょう。月々の通信費が大幅に削減できる可能性があります。PDF資料でも、通信費の目安として格安SIMの費用が提示されています 。
- 保険の見直し:
- 加入している保険が、本当に今のあなたに必要な保障内容と保険料になっているか見直しましょう。不要な特約や重複している保障がないか確認し、保険料を削減できる可能性があります。
- 住宅費・車の維持費など:
- 住宅ローン金利の見直しや、車の維持費(駐車場代、ガソリン代、車検代など)が高いと感じる場合は、ライフスタイルに合った選択肢(公共交通機関の利用、カーシェアリングなど)を検討するのも良いでしょう。PDF資料でも住居費や交通費の目安が示されています 。
固定費は一度見直せば、毎月自動的に節約効果が続くため、「無理しない」貯蓄の強い味方です。
第6章:「いざ」という時の備え:リスクと詐欺対策も忘れずに
老後資金作りは、着実に貯蓄と投資を進めるだけでなく、「いざ」という時に資産を守る視点も欠かせません。特に40代・50代は、親世代の老後や自身の健康など、様々なリスクが顕在化する時期でもあります。
6-1. 投資のリスクを正しく理解する
投資は元本保証ではないため、リスクを伴います。しかし、リスクを必要以上に恐れる必要はありません。大切なのは、そのリスクを正しく理解し、コントロールすることです。
- 価格変動リスク: 株式や投資信託の価格は変動します。しかし、長期・積立・分散投資を心がけることで、短期的な価格変動の影響を抑えることができます。
- 為替変動リスク: 海外の資産に投資する場合、為替レートの変動によって資産の価値が変わる可能性があります。
- 信用リスク: 投資先の企業や国の財政状況が悪化した場合、投資元本が失われる可能性があります。
これらのリスクを軽減するためには、新NISAの「つみたて投資枠」のように、投資先が厳選されており、自動で分散投資が行われる仕組みを活用することが有効です。
6-2. 老後資金を狙う詐欺の手口と回避策
残念ながら、高齢者や老後資金に関心のある人を狙った詐欺は後を絶ちません。詐欺から大切な資産を守るための知識を身につけましょう。
- 「必ず儲かる」「元本保証で高利回り」といった甘い誘いには乗らない: 投資に「絶対」はありません。特に「元本保証で高利回り」を謳う話は、詐欺の可能性が極めて高いです。
- 未公開株や社債の購入を勧める手口:
- 「もうすぐ上場する」「今しか買えない」などと言って、価値のない未公開株や社債を購入させようとする詐欺が多発しています。
- 親世代への注意喚起:
- ご自身の両親や親族が詐欺被害に遭わないよう、定期的にコミュニケーションを取り、怪しい話を持ちかけられていないか確認することも大切です。
詐欺から身を守るための行動:
- 知らない電話番号やメールからの連絡は無視する: 身に覚えのない連絡には応じないことが基本です。
- 安易に個人情報を教えない: 氏名、住所、電話番号、口座情報などを安易に教えないようにしましょう。
- 一人で判断しない、誰かに相談する: 怪しいと感じたら、家族や信頼できる友人、金融機関、消費生活センター、警察などに相談しましょう。金融庁のウェブサイトなど、公的機関が提供する情報を活用し、詐欺事例や注意喚起を確認することも重要です。
6-3. 親世代の家計から学ぶリスクと対策
前回のインプット情報にもあったように、親世代の家計に関する問題(例:親自身の医療費・介護費、実家の空き家問題、認知症と財産凍結など)は、40代・50代の私たち自身の老後資金計画にも大きな影響を与える可能性があります。
- 親の資産状況を確認する:
- 可能であれば、親の資産状況(預貯金、不動産、借金など)や、加入している保険、年金受給額などを把握しておきましょう。
- 介護費用や医療費のシミュレーション:
- 介護が必要になった場合や、大きな病気をした場合にどのくらいの費用がかかるのか、親と話し合い、シミュレーションしてみましょう。
- 「もしも」の時に備える:
- 親が認知症になった場合など、判断能力が低下した際の財産管理について、成年後見制度や家族信託などの仕組みについて調べておきましょう。
- 実家が空き家になった場合の管理や売却についても、早めに話し合っておくことが重要です。
これらのリスクに事前に対処することで、予期せぬ大きな出費が自身の老後資金計画を狂わせることを防ぎ、安心して老後資金作りに取り組むことができます。
第7章:お金と心と体のバランス:老後資金は「生きがい」のために
老後資金作りは、単にお金を貯めることだけが目的ではありません。大切なのは、そのお金を使って、どのような老後を送りたいのか、そしてその老後を健康で豊かなものにするための準備です。
7-1. 「お金」と「健康」は老後の両輪
どんなにお金があっても、健康でなければ豊かな老後を送ることはできません。40代・50代から、老後の健康にも意識を向けましょう。
- 定期的な健康診断: 早期発見・早期治療のためにも、健康診断は毎年必ず受けましょう。
- 適度な運動とバランスの取れた食事: 無理のない範囲で、日々の生活に運動を取り入れ、食生活にも気を配りましょう。
- 医療保険・介護保険の見直し: 公的医療保険や介護保険でカバーされる範囲と、自己負担になる費用を理解し、必要であれば民間保険の活用も検討しましょう。
7-2. 「生きがい」を見つける老後プラン
老後資金は、あなたの「生きがい」を支えるためのものです。どんな生きがいを持って老後を過ごしたいか、具体的に考えてみましょう。
- 趣味や学び: 時間ができた時にやりたいこと(旅行、習い事、ボランティア活動など)をリストアップしてみましょう。それらに必要なお金も考慮に入れることで、貯蓄の目標がより具体的になります。
- 人間関係: 友人や地域の人々との交流は、心の健康に不可欠です。退職後も社会とのつながりを持ち続けるための計画も大切です。
- 「稼ぐ」ことへの意識の変化:
- 老後も働いて「稼ぐ」選択肢を持つことは、老後資金の不安を軽減するだけでなく、社会とのつながりを保ち、生きがいにも繋がります。
- PDF資料でも、多様な働き方(会社員、公務員、アルバイト、フリーランスなど)が紹介されており、年収の違いにも言及されています 。
- 今のうちから、定年後もできる仕事や、新しいスキルを学ぶことなどを検討してみるのも良いでしょう。
終章:まとめ:「無理しない」は「あきらめない」こと
「貯蓄が苦手」というあなたへ。
この記事でご紹介した「無理しない」老後資金作りのヒントは、いかがでしたでしょうか。大切なのは、以下の3つのポイントです。
- 家計の「見える化」でストレスをなくす:
- 完璧な家計簿は不要です。キャッシュレス決済と家計簿アプリを活用し、まずはざっくりとでもお金の流れを把握しましょう。
- 「先取り貯蓄」で、給料が入ったらまず貯蓄分を自動的に確保する仕組みを作りましょう。これは、まさに「家計管理」において「毎月の収支をプラスに」する最も効果的な方法です 。
- 新NISAで「お金に働いてもらう」:
- 少額からでも「つみたて投資枠」を活用し、全世界株式インデックスファンドなどに自動積立設定を行いましょう。複利の効果を体験し、効率的な資産形成を目指せます 。
- ライフプランで「未来」を「見える化」する:
- 漠然とした老後の不安を、具体的な「ライフデザイン」と「ライフプランニング」によって明確な目標に変えましょう 。
- 年齢ごとの収入・支出や貯蓄の推移をシミュレーターで「見える化」することは、目標達成への強力なモチベーションになります 。
- 人生の3大費用(教育、住宅、老後)を意識し、計画的に準備を進めることが重要です 。
そして、忘れてはならないのは、詐欺対策や親世代の家計問題への備え、そして健康維持への意識です。これらは、せっかく築いた老後資金を守り、豊かな老後を送るための重要な要素です。
40代・50代は、老後を見据えた資金計画を立てる最後のチャンスであり、まだまだ十分間に合います。焦る必要はありません。「無理しない」をキーワードに、あなたのペースで、今日から一歩を踏み出してみましょう。
「貯蓄が苦手」は、もう言い訳にはなりません。あなたの未来は、あなたの手で変えられます。希望に満ちた「無理しない」老後資金作りを、今すぐ始めてみませんか。
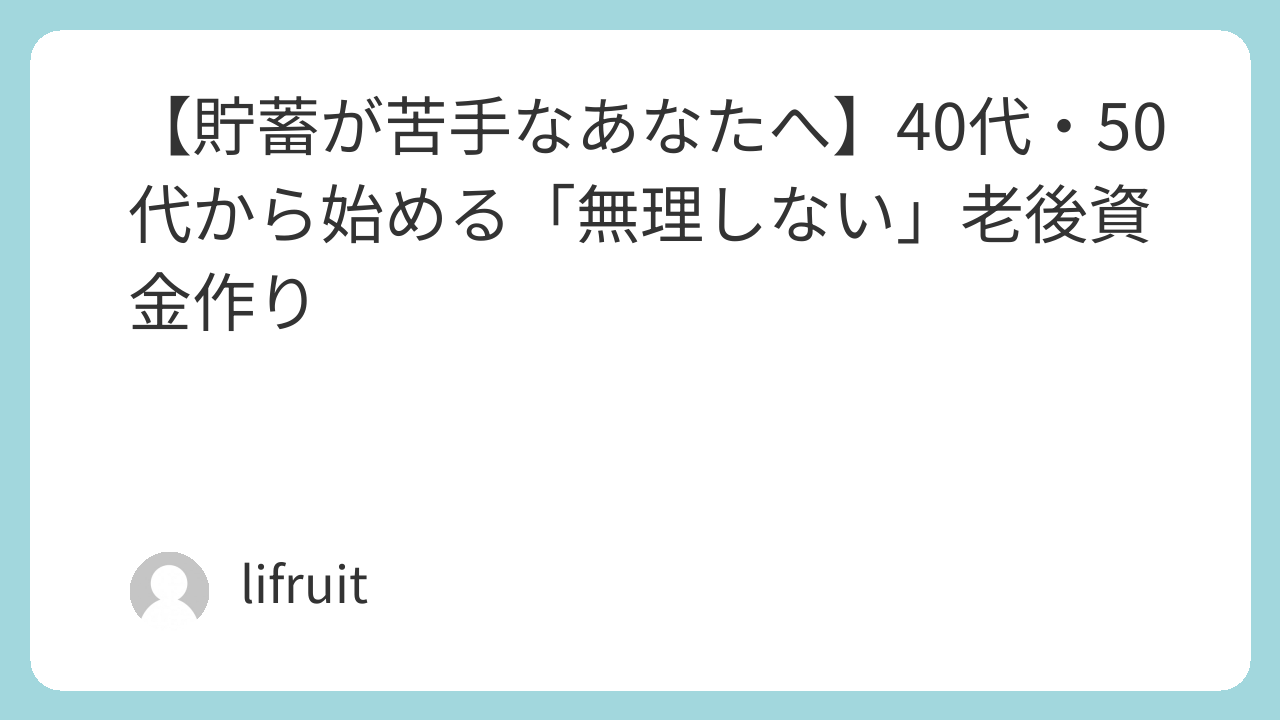
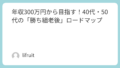
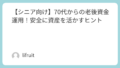
コメント